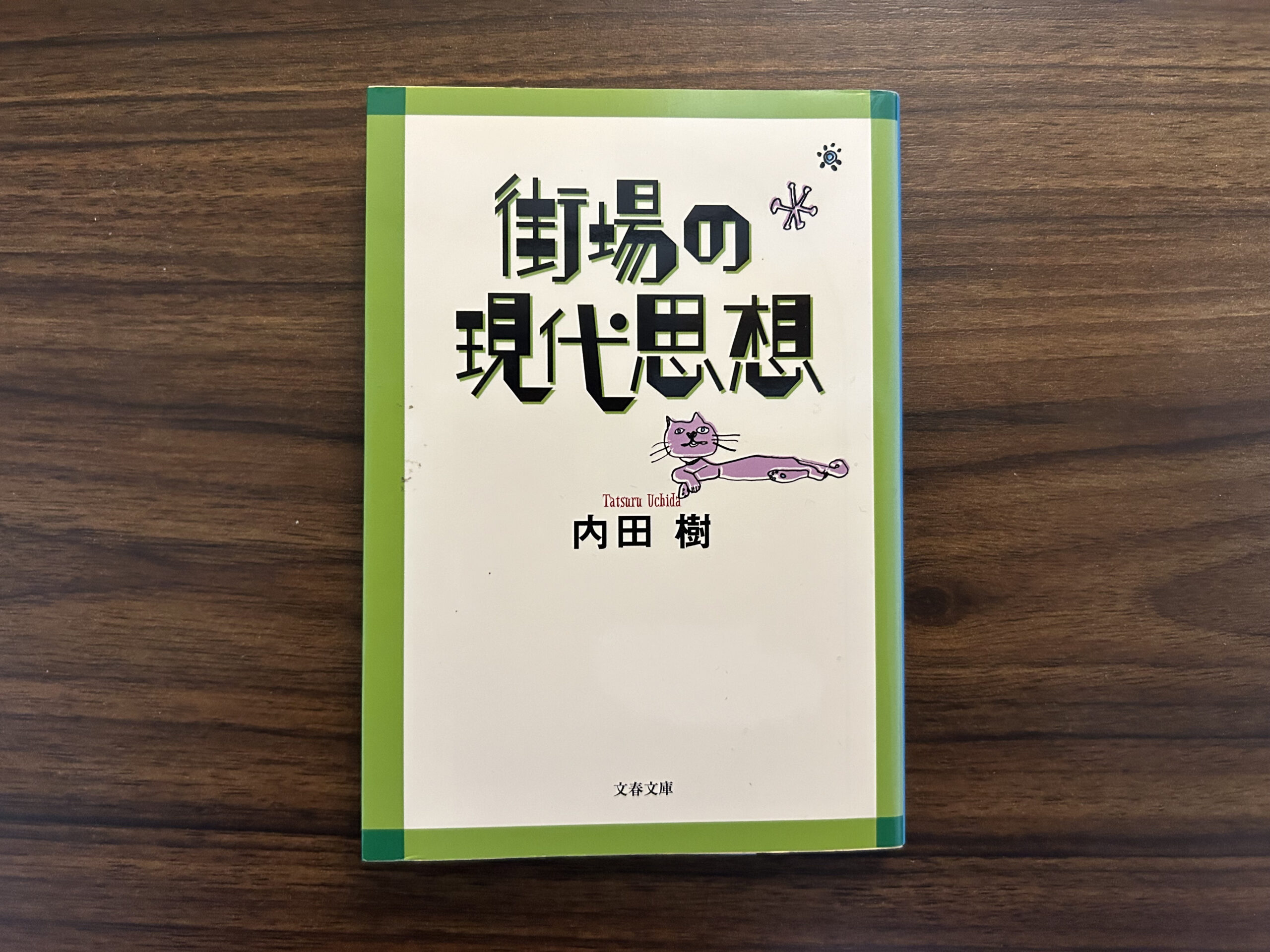『街場の現代思想/内田樹』を読む。
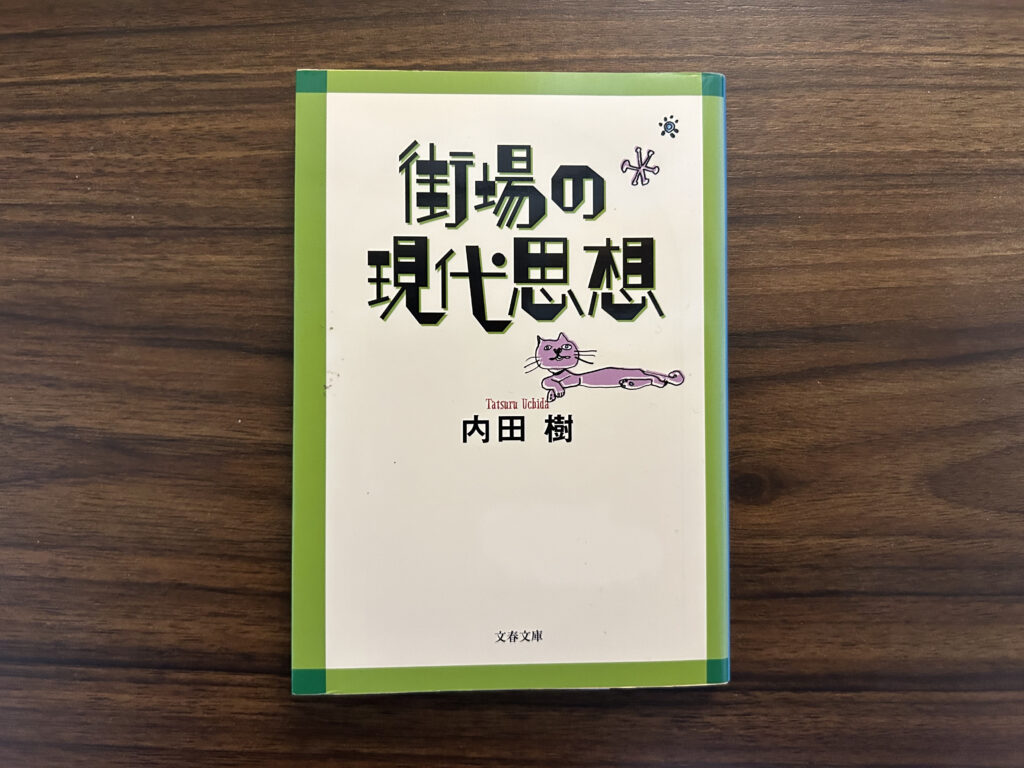
こんにちは。今年も春めいてきたと思ったら、僕の住む滋賀県は突然の豪雨。みぞれのような雨粒や雪もちらほら。近頃の天候は猫の目みたい。昨冬は関東にいたのでしばらくぶりの雪に感動しているけれど、雨具は不要かなと手ぶらで外出すると、瞬く間に大雨になったり。移動手段が基本バイクなので、季節の変わり目は毎度ヒヤヒヤしながら外出している。
さて、今回は最近読んだ本を紹介しよう。
人文書に親しみのある読者からするともはや説明するまでもない書き手、内田樹さんが上梓された『街場の現代思想』(文春文庫)である。上梓されたと言っても、本作の下敷きとなる単行本は2004年にNTT出版から刊行されており、いささか古い本なのだ。内田さんの本は高校生の時分からしこたま読んだし、あえて手に取る必要はなかったのだが、ここまで来ると全作読破してしまいたい欲求に駆られ、都合2日間ほどで通読した。むろん本作でも内田節が炸裂し、その独特の理路にいつも通り平伏するばかりである。
本作は、内田さんがもともとブログに認めていた雑文と、関西の情報誌で公開されていた人生相談の内容を合体させたもの。内田さんの書く街場シリーズでは、字義通り、市井の人々から寄せられた身辺相談を丁寧に解きほぐし、極めてクリアカットな論理で回答を提示するとともに、そこに内田さん特有の鋭角な知見が散りばめられている。それだけでなく、いつか実の娘さんである内田るんさんとの対談で「お父さんの文章はわざと音読しやすいように書かれてるでしょ?」と問われ、「その通りだよ」と内田さんが答えていたように、流れるような文体が読んでいて独特の愉悦を喚起してくれる。読むというより、聞く行為に近い。かといって平明すぎるわけでもない。読者に向けた熱烈なメッセージであると同時に、あくまでも読者を下に見ない文体である。
僕は高校生の頃に内田さんの書物に触れ、難読漢字や読み慣れない熟語に狼狽した記憶もある。とはいえ、内田さんの書き物から得た語彙は、僕にとって計り知れない財産である。読書を通じて言葉を知ることの利点は、単語帳のそれと違い、言葉を思い出すたび、いつまでも書き手のことを思い出せることである。多くの言葉は、書き手とともに今も抱き合わせで頭に収納されている。読書で身につけた言葉はそう簡単に記憶から剥落しない。言葉の手触りが違う。
閑話休題。
さて。本作はのっけからピエール・ブルデューの文化資本論に始まり、酒井順子(サカジュン)の『負け犬の遠吠え』の書評など、いささか張り切ったスタートを切るのだが、第3章以降は徐々に連載時のゆるめな人生相談に移行し、お金や結婚、学歴や転職についてなど、身近な話題がどしどし登場してくる。
ランティエ/rentierという暇人たち
殊に興味を引いたのは、『負け犬の遠吠え』の書評が出てくる第2章だ。内田さんは同作での酒井さんの論点を引き継ぐとともに、現代日本で急増している「30代、未婚、子ナシ」という負け犬(©︎酒井順子)について一考している。この定義は、世人からすれば確かに負け犬かもしれない。でも例えば、近代的な教養文化や芸術活動を担った人々って、実は大方この定義でいう負け犬なんじゃないか、という内田さんの問いかけ。現代日本の負け犬は往々にしてグルメ、海外旅行、歌舞伎、バレエ等のエンターテインメントに興じている。あながち独身者も悪くなくないのでは、という問いかけである。
確かにブルデューは、後発の”学習された文化資本”を持つブルジョアジーは結局、幼年の頃から高度な文化に親しんできた”身体化された文化資本”を持つ貴族層に勝てっこないと言いたがる。しかし、努力して文化的素養を身につけた人々がいなければ、文化産業というもの時代、今の時代まで残っていたかは不透明である。
ここから内田さんは「ランティエ/rentier(金利生活者)」という存在を思い出す。ランティエとはフランス語で、欧州を舞台とし、主に国際による金利や地代で生計を立てていた高等遊民たちのことである。その実、「我思う故に我あり〜!(コギトエルゴスムというラテン語にするとハリーポッターの魔術みたいな言い方になる箴言)」と言い放ったフランスの哲学者ルネ・デカルトの時代から1914年の第1次世界大戦勃発まで、ヨーロッパでは貨幣の価値があらかた一定していた。ヨーロッパの家は石造りで、祖先から譲り受けた家具や什器をそのまま使用できる。つまり、祖先が一度アパルトマンと国債を購い、レガシーとして継承してしまえば、その末裔や相続人たちは終生、安逸な生活が約束されていたのだ。そうか。サカジュンのいう負け犬は、家族や身内の束縛が比較的軽い、現代のランティエとも言えそうだ。
内田さんはそんな現代のランティエを歓迎する。だって、学問や文化、芸術という営為は古来から、ランティエのような”暇人”によってしか始まってないんだから。まぁ、悲しいかな事実だろう。
僕も古代ギリシア哲学を学んできた身として賛同したい。古代ギリシアでは「テオリア/theōria」という活動が重視されていた。テオリアというのは、かつてのギリシア語で「観想」や「眺めること」を意味する。これは万学の祖アリストテレスなどが最も重宝していた活動、いや人間にとって至高の時間だと激賞していた行為である。要は、暇を作ってあれこれ世の中の真理とか(そんなんあるのか)、最近の芸術とか(僕は知識が足りひん)についていたずらに考える時間が人間にとって一番幸福なんやと。詳しくは『ニコマコス倫理学』とかを参照ください。光文社から出版されてる渡辺邦夫先生の翻訳がおすすめ。
※ちなみに僕は「友愛」についての章が大好き。友達付き合いの本質を2000年前から書き尽くしている。ザ・碩学。
もしプラトンが週休2日、1日8時間労働の生活を送っていたら、「国家ってなんやねん」という疑念なんか絶対に湧かない。というか、中期の代表作『国家』でぞろぞろと集まってきたあの名だたる論客たちを「議論しましょや〜」と集めることすら、不可能に近かっただろう。いま”フルタイムで働くプラトン”を想像して、書きながら笑ってしまったが、それぐらい想像できない。 誰か街中の小売店かどこかでプラトンらしき人物を見つけたら教えてくださいませ。
それはさておき、元より古代ギリシアは奴隷制を平然と採用していたし、アリストテレスのような社会の上層、有閑階級の人たちのみが、有り余る時間を駆使して思索にふけることができたのである。労働、特に家事は当時、蔑まれるべき行為として映じていた。この辺、学問に携わる人や本読み、ディレッタントは、僕も含め存外ゆるがせにしている気がする。「学問って時間なかったらでけへんねん」という当たり前の前提を、今一度考えたい。人間が1日に使えるエネルギーには限界がある。
だってそうやろう。今一番売れている新書は『なぜ働いていると本が読めなくなるのか/三宅香帆著』である。2025年の新書大賞も獲った。「ものを読む」という行為は、古来から学的営為のキホンのキである。その行為がみんな出来なくなっている。構造的に出来なくさせられている。別に時間のある人が暇に任せて学問でもしとったらええやんと思われそうであるが、これは著者である三宅さんの意図でもあると拝察するけれど、学問や書物の世界は、多様なアクターが関わり合わないと、べらぼうにおもんなくなるのである。労働か思索か、どちらか一方ではなく、多様なアクターが書き物という媒体を通じて接しあうことで生まれる創造性を、現代の労働環境は阻んでしまっているのである。ランティエに戻ることはできない。ただ、僕たちの中に”ささやかなランティエ”を育む活路はどこかにあるはずだ。
今日はここいらで。大学人は管理業務に忙殺され、労働者は全身全霊で働くことを構造的に強いられる今日だが、近頃は労働の中に知的営為が組み込まれている側面もあり、完全に労働と学問、文化を切り離すことはできないのだろう。それにしても労働という、対価がある程度明白な行為に比して、学問や文化は必ずしも即座にその良質な果実を思い描くことはできない活動である。暇と学問、労働についてのテオリアは続く. . .